この記事の印刷用データは こちらよりダウンロード頂けます。

MEMORIES
エーデルワイス創業者
比屋根 毅
「おいしい」とは何か。
一切の妥協を排し、追求をやめない姿勢に弟子たちは鼓舞され、可能性を具現化する力は、縁を授かった一人一人の財産になった。日本の洋菓子界の発展に、この人の足跡がある。ゆかりのある人々へのインタビューから、次世代に残したい言葉の数々を綴る。
(執筆・編集/ 座安あきの Polestar Communications)
愚直さ、度胸の人、意志貫徹、時代の寵児。後にも先にも、こんな人はもう現れない–––––。
日本の洋菓子文化の発信地、兵庫・神戸を拠点に「アンテノール」「ヴィタメール」など人気の高級洋菓子ブランドを築いたエーデルワイス。1966年の始まりから54年。2020年6月4日、82歳で亡くなった創業者・比屋根毅氏を知る人々から語られる、この特別な存在感。
15歳で故郷の沖縄・石垣島を離れ、洋菓子職人の道へ。業界のカリスマと称された。商店街の小さな店舗を、一代で業界随一の100億円企業に育て上げた経営手腕だけではない。菓子職人として、技術に向き合う「真剣」を自らの鍛錬で見せた。「夢」は口にした瞬間から、実現させるシナリオが描き出されることを身をもって示し続けた実力者でもある。
憧れた圧巻の技術者集団
今から40年前。大阪で開かれた工芸菓子のコンテスト会場。菓子材料を使って造形の美や精巧な技を競う一流菓子職人の登竜門に、関西圏を拠点にする有力パティシエが大勢集まっていた。緊張感漂う雰囲気の中、一角だけ異なる熱を発している集団があった。白衣姿の菓子職人がずらりと並ぶ圧巻の記憶が、パティシエ・牧野眞一さんの脳裏にはっきりと蘇る。
「エーデルワイスの技術者集団が、向こうからバーっと現れる。これがもう、とにかくかっこいいんや」
現在、大阪府豊中市で人気店「ケーキファクトリー ムッシュマキノ」を経営する牧野さんは当時、20代後半。個人経営のケーキ店で修行を積み、年1回開かれるコンテストで上位入賞者の常連に食い込んでいた。
一方、エーデルワイスは洋菓子メーカーとしては珍しくフランチャイズチェーン事業を展開。「エーデルワイス」名の店舗ブランドと、創設したばかりの「アンテノール」とともに、次のステージへと向かう胎動期にあった。代表的な職人には、津曲(つまがり)孝さんの存在が注目されていた。

ケーキファクトリー・ムッシュ マキノ
牧野 眞一 氏
The Cake Factory Monsieur Makino
憧れの世界へ、注目の的
「今年の優勝者は津曲、翌年は牧野というのが4回くらい続いたころ、ある時比屋根さんが店にやってきた。『牧野くんよ、来週時間あるか』って」。
スカウトだった。20坪ほどの小さな個人店で働いていた牧野さんをバーに呼び出し、比屋根氏はプロ野球界の2人の巨匠になぞらえてこういった。
「僕は君を長く見ている。うちには王か長嶋、どちらかわからないけど1人いる。津曲が長嶋だったら、王がいない。牧野くん、どうかな」。
初めての会話はほんの10分ほどだった。憧れのエーデルワイス。すでに大物経営者として知られていた比屋根氏を前に、牧野さんは緊張で全身を固くしていた。
「1日15万円ほどしか売り上げのない小さな店からいきなりエーデルワイスなんて。150店という店舗数にもびっくりした。僕は自転車だけど、比屋根さんはジャガーに乗ってはる。本当にすごい世界やなって。こんなケーキ屋があるんかなって思っていた」。
それまで、10年間お世話になった店をそろそろ卒業して、自分の店を持ちたいと考えていた矢先の突然の誘い。「ちょっと悩んだ」と振り返る。
その翌年のコンテスト会場には、エーデルワイスの紋章をつけた白衣に身を包む牧野さんの姿があった。隣には津曲さん。会場に到着するやいなや、参加者の視線が一気に自分に注がれるのを肌で感じたという。「来た来た来た、あの牧野が一緒に並んでいる。エーデルに行ったんやなって」。
期待を超える 自信の布石に
所属するパティシエが、数々のコンテストで上位入賞し続ける“職人集団”。コンテスト会場で牧野さんが目の当たりにした威風堂々たる職人たちの姿は、比屋根氏が自らを起点に掘り起こし、寄り添い、積み重ねてきたエーデルワイスの企業文化そのものでもある。
「世界パティスリー2009」で優勝した日本チーム。右から3人目がエーデルワイス社員(同社提供)
小規模の個人店で密な師弟関係を築きながら腕を磨いていく形態とは一線を画した。比屋根氏が創り上げたのは、技術者の育成と輩出、そして彼らの舞台となる事業の拡大、その両方をかなえた“未踏”の世界だった。
エーデルワイスは創業から12年後の1978年に、異人館のある神戸・北野町に素材にこだわった高級路線の「アンテノール」を創設した。阪神百貨店に、でき立てのケーキを提供する厨房付きの店舗を業界で初めて出店したのはそれから3年後のことだった。
この店舗を皮切りに、百貨店からの出店依頼が相次ぎ、アンテノールは関西圏から首都圏、全国主要都市へ、デパート銘店の一等地の顔としてその名を知らしめていくようになる。店舗展開と並行して比屋根氏が重点を置いたのが、本物の味を生み出す技術力の向上と、商品開発の研究だった。フランスパンを主力商品にした「ル ビアン」を出店した同じ年の1982年、洋菓子業界では初めて「中央研究所」を尼崎市内に設立した。商品づくりを極める精神が受け継がれる源泉となった。
1981年、エーデルワイスの一員になった牧野さんは、比屋根氏率いる職人たちの中で、これまで経験してきた以上に厳しい修行に打ち込んだ。一つ一つのことに妥協を許さない比屋根氏の振る舞いに圧倒されながらも、揺るぎない仕事への向き合い方に共感していたという。
「エーデルに入ってから一つだけ、心がけたことがあった」と牧野さんは明かす。「絶対、期待を裏切らないこと。あそこ(エーデルワイス)には歴史と伝統がある」。だから、2番ではだめだった。牧野さんは常に1番であることを自分自身に課し続けた。

牧野氏は、1968年洋菓子業界へ。72年ドイツに修行で渡る。83年第1回全国洋菓子技術コンテストでアメリカ農務長官賞受賞後、ワールドケーキフェア内閣総理大臣賞(1位)、世界洋菓子コンクール日本代表で13カ国中1位、第5回全国洋菓子展示大品評会内閣総理大臣賞など、多数の受賞歴がある=10月14日、大阪府
「できるように工夫して見せろ」
「夕方現場にふらっと入ってきて比屋根さんがこういう。おい牧野よ、あのケーキ、明日出社するまでに1万個作ってもらえんかって。1日の仕事の終わりかけ。片付けを始めているところなのに。比屋根さんはもちろん知っていて言っている。僕は必ず『はい、わかりました』と答えた。営業や経理は『今から無理ですよ』というけど、そんなことはわかっている。他の人と僕の違いはそこにあると思っている。あくる朝、また比屋根さんが来て『どうだい、いくつできたか』と聞く。『あれから精一杯やって。材料の調達から始めたので、ここまでです』というと、一言『そうか』とだけ言って帰っていく」
指示することの意味を一つ一つ説明などしない。だが、牧野さんにはわかっていた。無理だと思うことを「無理だ」で終わらせるな、できるように工夫してみせろ、という投げかけだと。他の誰でもない、牧野さんには平気で無理難題と思えるような投げかけをした。そんな要求はある意味、牧野さんにとって認められたような、誇りでもあったのかもしれない。要求に応えていくことがいつしか、自信につながる布石になっていたことに、後から気付かされることも少なくなかった。
熱意で動かした 名門との提携
比屋根氏は自身の修行で培ったネットワークを生かして、社員を繰り返しヨーロッパの菓子メーカーに研修に行かせた。老舗、本場の有名店ばかり。門外不出の伝統的な菓子づくりの現場に立ち会える経験の重みが一人一人にとって血となり肉となり、絶え間なく技術を磨き続ける職人世界で大いなる糧となった。
牧野さんはこう振り返る。「身体で覚えろ、どんな材料が使われているか、ゴミ箱の中に何が入っているかまで覚えるくらいに打ち込め、と。そんな思いで送り出してくださった。研修から帰ってきても、比屋根さんは『覚えたルセット(レシピ)であそこのお菓子作って見せろ』なんて絶対に言わない。技術者をよく信用して、勉強する場をたくさん与えてくれた」
ベルギー王室御用達の有名菓子店「WITTAMER(ヴィタメール)」との技術提携、日本初出店は、エーデルワイスにとっても業界にとっても画期的な出来事だった。
世界中から提携オファーが絶えなかったという老舗の名門ブランド。創業店以外の出店を断り続けてきたというオーナーが、比屋根氏の菓子づくりに対する熱意に動かされ、初の技術提携へと動いた。1989年に業務提携を結んだ後、比屋根氏は数十人の技術者をベルギーへ送り、「ヴィタメール・ジャポン」独自のレシピを完成させた。牧野さんは、その研修者の中心的な一人となり、初出店にも携わった。
ヴィタメールは初出店から今年30周年を迎えた。国内有数の高級チョコレートブランドとして変わらぬ存在感を示し続けている。

ヴィタメールベルギー本店(エーデルワイス提供)
「何にもないところから、自分でそうしようと決めたら、本当にそうなっていく。ヴィタメールに行って、お店とお菓子に惚れて、これをなんとか日本に持ってきたいと思ったら本当に実現した。ヴィタメールの店の前に座禅のごとく5日間、了解を得るために立っていたとか言う。ほんまかいなと思うような、ものすごい逸話がなんぼでもある」と笑う。
業界育てた“時代“の目撃者
比屋根氏のことを、ある人は「オーラがあった」といい、ある人は「怖くて近寄りがたかった」という。姿を現しただけで、その場の空気が変わった。忙しい現場でも皆、手を止めて出迎え、車が見えなくなるまで見送った。扉に近づくと、さっと誰かがその先に回り、通り道を開けた。仕向けるわけでもなく、比屋根氏は周りが自然とそう動くような、目には見えない威厳を放っていた。
だが、様々な場面の、異なる印象的な表情を、牧野さんはいくつも知っている。「会長には、僕らが想像を絶するくらいのロマンという欲望があった。単純でものすごくかわいい人。ものすごい勝負師でもある。度胸がある。ちっこいのにかっこいいんや」。今も、すぐ近くにいるように、比屋根氏を物語る言葉が、止めどなくあふれ出てくる。
見つめた生き様と仕事
牧野さんにとって「絶対に裏切らない」と決めた比屋根氏とは、どんな存在だったのか。「師でもない、父親でもない、なんだろうか」と考えあぐね、最後にこう言った。「一人の男として、かな」。
比屋根氏の生き様、仕事を一番近くで見つめた。職人との関わりを通して、日本における洋菓子という一つの文化と技術を編み上げ、組織の垣根を超えて仕事に携わる人々が互いに影響を与え合う世界観をつくり上げた人。牧野さんは、「比屋根毅」という“一時代”の目撃者だったに違いない。
牧野さんは独立した後も何度も比屋根氏に呼ばれては、すぐに会いに出かけたという。
「周りは独立したのにいつまでゴマ擦っているのかっていう人もいたけど、そんなつもりはない。体が反応するんだ。それなのに、俺の前で『調子が悪い』というのは許せなかった。亡くなりはった時にも、俺はなんや腹が立ってきて、腹が立ってきて。ご家族がいる前で思わず『なにしとんねん』って言ってしまったんや。俺は強い姿しか見たくないから。なんぼ会社が傾きそうな時も、いろんな大変なこともたくさんあった。でも、あの人は常にジャガーなんや。ずっと、あれに乗っていてほしかった」
夢語らう、超一流の職人仲間
「会長を知った時、この人はだたの人じゃないなと思った。業界の中で、事業的にも商品的にも一人であれだけのものを作り上げた人はなかなかいない。業界の地位を高いところに持っていく、全国に舞台を作っていく、政治家的なパワーと説得力があった。もうあんな人は出てこない」

オーボンヴュータン・オーナーシェフ
河田 勝彦 氏
AU BOU VIEUX TEMPS
東京都世田谷区にある高級フランス菓子の店「オーボンヴュータン」のオーナーシェフ・河田勝彦さんは、国内の洋菓子業界における比屋根氏の"迫力"をこう表現する。
河田さん自身、1960年代、20代で本場フランスに渡り菓子職人として修行を積んだ。河田さんの下で技術を学んだ職人は200人を超える。「現代の名工」にも選ばれた、洋菓子職人の第一人者として知られている。

オーボンヴュータン尾山台店
比屋根氏とは15年ほど、東京と神戸を互いに行き来しながら交流を続けた。職人気質な者同士、2人は会うと仕事の話ばかりしていたという。
「比屋根さんが日本に持ってきたベルギーのヴィタメール、私も比屋根さんが入るより1年前にそこにいたんですよ。ヨーロッパでも5本の指に入る。すごかった。どうしてもあそこのチョコレートをやりたくて」
ハングリー精神のあった時代、
職人のあり方にも変化
晩年、比屋根氏は河田さんにヨーロッパへの出店や、菓子職人のための教育機関創設の目標を語っていたという。河田さんは冷めることのない比屋根氏の情熱に思いを馳せると同時に、これからの「職人」に対する憂いにも似た、危機感にも言及した。
「僕は今76歳で、終戦間際に生まれています。僕の中で、あの時代なりのハングリー精神というか、飢えを感じているし、選択肢なんてなかった。贅沢なこと言ってられない。食うための手段として菓子職人を選んだ。今の子たちのように、続かないのなんだのというのは、あるわけがない。今の時代で思う職人と、50年前に僕が始めた職人の考え方は違ったと思う。コロナの状況になっても、若い人たちの考え方はどんどん変化している。10年もしたら職人はゼロになるかもしれませんね」
しかし、どんなに環境が変わっても、比屋根氏は夢をあきらめなかった。業界全体のために何ができるかを常に考え、実践していたことに、河田さんはただただ、敬意を込めて向き合っていた。
「あの方は夢を語った。僕なんかよりずっと強い思いがあって。僕なんて弱っちい人間ですから、あの方の考えについていこうと一生懸命でした。日本の洋菓子のために、もっと引っ張っていって欲しかった」と惜しんだ。
最大限に生かす創業者の光
幼い頃から自宅に併設した店舗で、働く父親の姿を見ながら育ったエーデルワイス代表取締役社長の比屋根祥行氏。菓子職人の道には進まなかったが、ブランド開発と店舗展開に直接関わり、経営者としての父の判断軸を目の当たりにしてきた。

エーデルワイス代表取締役社長
比屋根 祥行 氏
President&CEO of EDELWEISS
フランチャイズ事業からの撤退、「アンテノール」「ヴィタメール」「ル ビアン」の創設、そして自身が中心になって立ち上げた焼き菓子とフレッシュケーキの店「ノワ・ドゥ・ブール」の新宿伊勢丹への出店などを経験した。コンビニエンスストアの台頭や百貨店の再編など、経営環境が大きく変わる中、時代を見極め、戦略を立て、計画を着々と実行に移していく現場の息吹に触れた。
父の故郷・沖縄への出店では1980年代に一度、実現を目の前にして断念した経緯があった。県外企業の進出に対する地元業界の懸念を払拭することができなかったためだ。創業50周年を間近に控えた2014年、30年越しの計画を進めるために、「恩返し」の思いを沖縄の人々にどう伝えていくか、腐心する比屋根氏の姿が心に残っている。
「沖縄での開業セレモニーのために工芸菓子(ピエスモンテ)を本社で作って、きれいに梱包し、飛行機で運んだ。会長夫婦と家内と私の4人がかりで抱えながら。離着陸の時も揺れないように持ち上げながら慎重に慎重に。生まれ故郷の沖縄の皆さんに洋菓子の文化を伝えたい、恩返しをしたいという強い思いが伝わってきた」
身内にも容赦なく厳しかった比屋根氏とは、公私に関係なく何度もぶつかってきたという祥行氏。だが、同じ職場で息子であることに、「窮屈さを感じることはまったくなかった」と語る。
「創業者の息子や娘であることが、嫌だという人もいるかもしれないが、それは違うと思っている。立場を最大限生かす。七光どころか、八光、十光くらい生かし切ることが、次の代が成功する秘訣だとある人に教わった。例え新しいことを始めるにしても、先代の光を大切に受け継いでいきたい」
魅せる、原点の味
サクッと音が鳴るほどの軽い食感。ふんわりとしたシュークリームらしい見た目は一瞬で裏切られる。意外な驚きと同時に、中からカスタードと生クリームいっぱいの甘い風味が押し寄せてくる。「ケーキハウス・ツマガリ」の定番商品、「シュー・ア・ラ・クレーム」。
「おいしい?そうでしょう。これが、エーデルワイス初期の原点の味」と、津曲さんは誇らしげにいう。エーデルワイスでアンテノールの社長を務めていた頃に自身がつくり上げた味だという。

ケーキハウス・ツマガリ
津曲 孝 氏
The Cake House TSUMAGARI
「練り粉菓子の原型。カリフラワーに似ていないとダメ。ふくらし粉も入っていない。自然の空気でもない。化学薬品など一切入れずに化学式を持っている大地の水から作る。グルテンを柔らかくして、小麦粉のデンプンを膨らませてくれるいい水がないと作れない。日本の硬水がいい。それを使うとパーっと膨らむ」

サクッと香ばしいシュー皮にたっぷりのクリームを詰めたケーキハウスツマガリの「シュー・ア・ラ・クレーム」
津曲さんは宮崎県の貧しい農家に生まれ、祖母に育てられた。家計を助けるために14歳で上京。倉庫の荷役作業員や自動車の修理工から、東京での洋菓子店勤務を経て、知人の紹介でエーデルワイスに入社した。菓子職人としては全くの未経験から、独立独歩の感性と努力で腕を磨き、エーデルワイスの技術の高さを体現する職人の代表格になった。
貫いた独立心、信頼育む

見えない味に、身一つで勝負
「味(み)えない味(あじ)が魅(み)える」
菓子作りの根底にあるものは何かを尋ねると、津曲さんはノートにこう書き記した。答えの見つからない「おいしい」をかなえる世界。「見えない味を魅力的に見せる」ということをひたすらに求めてきたという。エーデルワイス時代に遡る「原点」は、今も、日々の仕事で忘れることはない。
津曲さんの生い立ちは、生まれ育った石垣島を15歳で離れた比屋根氏と重なる。互いに辺境の地から頼る者もなく都会へ出て、洋菓子の道一筋、身一つで自身の人生をつくってきた。
「僕らにとって会長が沖縄人とか、そんな感覚は全くなかった。僕も中学しか出ていないし、考え方が共通。会社には学閥も門閥もない。明るく元気で素直、この3つがあればすべてオーケーだった」と振り返る。
エーデルワイスでヨーロッパに派遣された第一号の職人。初めてチョコレートやショコラを商品づくりに取り入れたのは津曲さんだった。

人づくりについて語る津曲孝さん。「できない子を育てるにはコツがある。いろんなやり方で隈なく人を生かせば勝てる。でもそのためには、その人の自己のやる気が強くないとだめ。なんぼ頭が良くても、無我夢中じゃないといけない。そして、やる気があっても、状況がわからないといかん」=10月14日、西宮市甲陽園・ケーキハウスツマガリ
「心を強く、本物の芯のある男に」
一方、1987年にエーデルワイスから独立して自分の店を持った時から、津曲さんには「弟子」を卒業したという意識がある。
「独立したら一人で立つという意味。どんな動物でも巣立ったら呼び戻さない。自分の息子といえども突き落とす。自分の世界をつくり上げ、いろんな匂いを嗅がせると、アイデンティティーがちゃんと出てくるようになる。自分に勝たないと生きていけないから。誰も代わりにトイレに行けないのと同じ。自分の気が弱ったり、心を強くできなかったりすると、前に進まない。内面の強さのある、本物の芯のある男になりたい」
エーデルワイスで津曲さんと同じ時を共に過ごした牧野さんはこういう。「会長が一番信頼していたのは津曲だと思う。僕にはわかる」と。
津曲さんの意志の強さ、探究心、素材への強いこだわりは、「独立心」を貫いた比屋根氏が最も共鳴し、拠り所にした資質ではなかったか。エーデルワイスが誇る技術力の基盤づくりに、津曲さんの果たした貢献は大きかった。
島の子どもたちへ、贈るエール
比屋根氏は石垣島で8人兄弟の3番目として、サトウキビ農家に生まれ育った。7歳の時に終戦を迎えた。家庭は貧しく、少しでも家計の負担を減らしたいとの思いで早くから自立を目指した。15歳の春、両親に何も告げず、一人で那覇行きの船に乗ったという。
世界中を旅する夢をかなえられる職業を探し、洋菓子にたどり着く。技術を極めようと大阪に渡ったのは、沖縄が本土に復帰する前の1960年代。渡航にはパスポートが必要だった。自身の著書『人生無一事』(致知出版)で比屋根氏は、沖縄人というだけで差別を受け、深く傷ついた経験を語り、「『よし、何がなんでも日本一になってやる。いや世界一になってみせるぞ』という気持ちが沸々と湧き上がってきた」と記している。

大賀製菓時代に初めてつくった工芸菓子(エーデルワイス提供)
身体の内側からみなぎるエネルギー、悔しさをバネに努力を惜しまず、昨日より今日、今日より明日、もっと上手くなる自分を求め続けた。だからこそ、同じ故郷の若者の挑戦には、人一倍の情熱を込めてエールを送った。
「必勝ケーキ」で甲子園球児に声援
本土復帰後の沖縄県民の悲願、「甲子園優勝」を目指す球児たちの歓迎には特に力が入った。甲子園の開会式に合わせて沖縄から到着する100人余りの球児らの宿舎にケーキを毎年贈り届けた。今も続くエーデルワイスの恒例行事になっている。
「一人一人に1個ずつ、ケーキに必勝、必勝、必勝、必勝って、腕が痛くなるまで書いてね。沖縄の子たちのためのお菓子はほとんど、僕が担当した」と津曲さんは懐かしんだ。
1980~90年代に、豊見城高校、沖縄水産高校の野球部を甲子園出場、決勝進出へと導いた名監督・栽弘義氏のことを、津曲さんはよく覚えている。
「あの人には勝負師の圧力があった。やっぱり勝たせる能力を持っているんでしょうね。栽監督はとことん沖縄のグレードを引き上げましたね」と称賛する。年代を重ねるごとに、沖縄の子どもたちの雰囲気が段々とたくましくなっていく変化を肌で感じていたという。
沖縄の球児らの目覚ましい活躍が注目されたのと同じ頃、比屋根氏は1986年に横浜で開催されたワールドケーキフェアでグランプリを受賞、“世界一の洋菓子職人”の評価を得た。
その翌年、比屋根氏は石垣市内の母校の小中学校に図書費として100万円ずつを寄付している。97年に石垣市の市民栄誉賞を受けてからは、毎年市内の幼稚園、小学校、中学校に「学校図書充実資金」として100万円を送り続けてた。
人づくりに賭ける息の長い関わりは、“沖縄出身の世界一の技術者”としての責務とでもいうような、故郷の若い世代、子どもたちに向けた未来への種まきだった。

尼崎市内にあるエーデルワイス本社工場
挑戦の始まり、沖縄に技術を
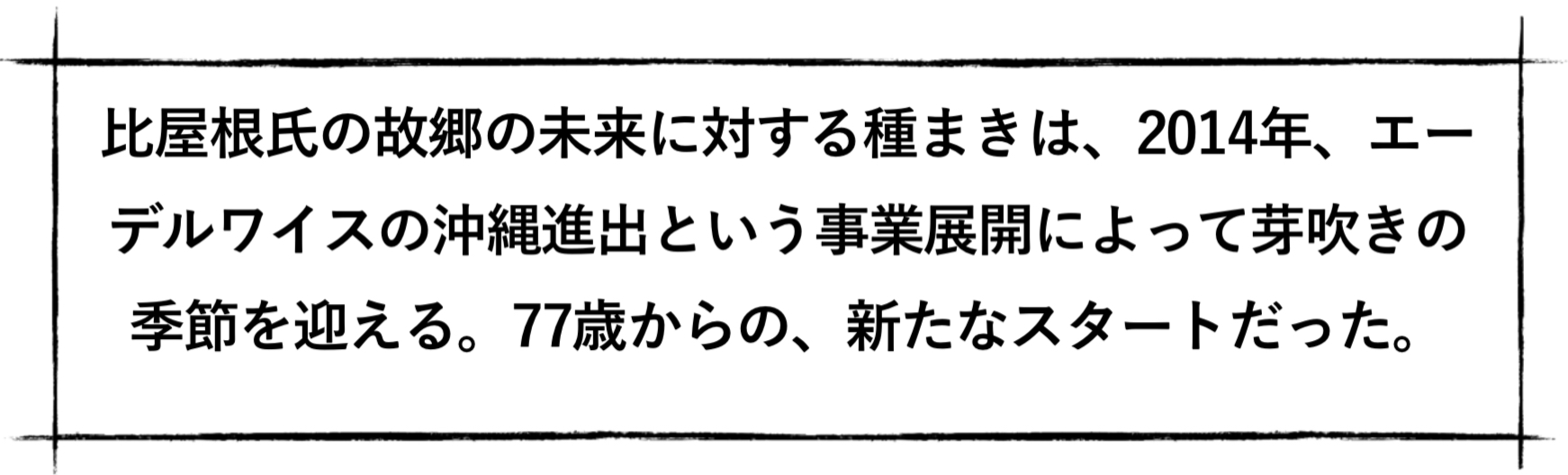

オキコ株式会社 代表取締役社長
銘苅 敏明 氏
エーデルワイス、沖縄出店検討
石垣市出身・比屋根会長 洋菓子大手–––––
沖縄の地元紙「沖縄タイムス」1面に、エーデルワイスの沖縄進出を報じる記事が掲載されたのは2014年2月10日。その7か月後の9月1日、エーデルワイスは地元の食品製造大手オキコ(西原町)と合弁会社を設立、翌15年2月には1号店を那覇市内に開業した。「2年以内に」という表明を、1年で実行に移した異例のスピード進出だった。
30年前に一度、計画して直前で頓挫した苦い経験のある沖縄進出。2度目の挑戦には、比屋根氏の思いだけではなし得ない、伏線となる“もう一つの熱意”があった。
比屋根氏が沖縄進出を表明するちょうど1年前。オキコ取締役だった銘苅敏明さんは一人、神戸市内にあるエーデルワイス本社を訪れていた。事業譲渡を受けて立て直しを進めていたオキコの自社ブランド「洋菓子のトレビアン」が思うように改善せず、業績が低迷していた。担当していた銘苅さんには、その原因がどこにあるか、はっきりとわかっていた。
「トレビアンの商品なんてお土産に持っていけないよ、美味しくない」
目の前に関係者がいることを知らないある客が、率直に吐き捨てた言葉が、決定的となった。
沖縄の課題解決 オキコの使命に

「技術とは」について語る比屋根氏の言葉を書き記した銘苅社長の手帳。毎日持ち歩いて、立ち位置を確認している。
「うちにはお菓子作りの職人がいなかった。商品開発をしようにも、現場とずっと平行線で意思疎通ができない。個人で内地に修行に行って沖縄に帰ってきた若い人たちの中には、小さな個人店でも成功している人がそれなりにいた。でも、トレビアンは会社。職人を募集しても誰も来ない。ずっと悩んでいた時に、『カンブリア宮殿』というテレビ番組で比屋根会長のお考えを知った。沖縄への思いがあるのであれば、ぜひお会いしたいと思った」
オキコの抱える課題は、沖縄の抱える課題そのものだった。沖縄県の産業は本土復帰後、長期にわたって観光産業や公共事業に支えられた。地元資本による製造業の基盤が乏しく、「ものづくり」に携わる職人が育ちにくい状況が続いてきた。
一流洋菓子職人の不在
オキコは終戦から2年後の1947年に、住宅復興に不可欠だった赤瓦の製造・販売で創業、その後53年に製麺・製パン事業に転じて60年余り。県内最大手の食品製造企業に成長した。国内製パン大手の敷島製パン(名古屋市)と技術提携を結び、早くから製造技術の獲得に力を注いできた。
一方、洋菓子の分野では苦戦した。伝統ある多種多様な菓子作りの基本を習得するだけでは足りない。発想力やデザイン力、繊細な技法などを身につけ、試合や舞台に出続けなければなければ、技術者は育たない。企業として、国内外で一流の評価を受けるほどの職人育成に成功しているケースは、オキコ含め県内では例がなかった。
「沖縄の経済は、企業の生産性が低い、ものづくりが弱い、そういう特性がずっと指摘されてきた。この課題の解消は誰がやるんだ、オキコがやらないといけないと思った。もう逃げられない、やるしかない、そう確信した」と、銘苅さんは振り返る。

「技術とは–––––」。ある日、会食の席で比屋根氏が何気なく語ったこの4つの言葉に、銘苅さんは電流が走ったように奮い立った。
「探していた言葉はこれだ」
技術が大切なことはわかる。でも、なぜそうなのか、裏付けとなる明快な言葉を持っていなかった。技術の体得者であり、実践者でもある比屋根氏によって言語化されて初めて、「心に落ちた」瞬間だった。
商品力で勝負、沖縄から全国へ
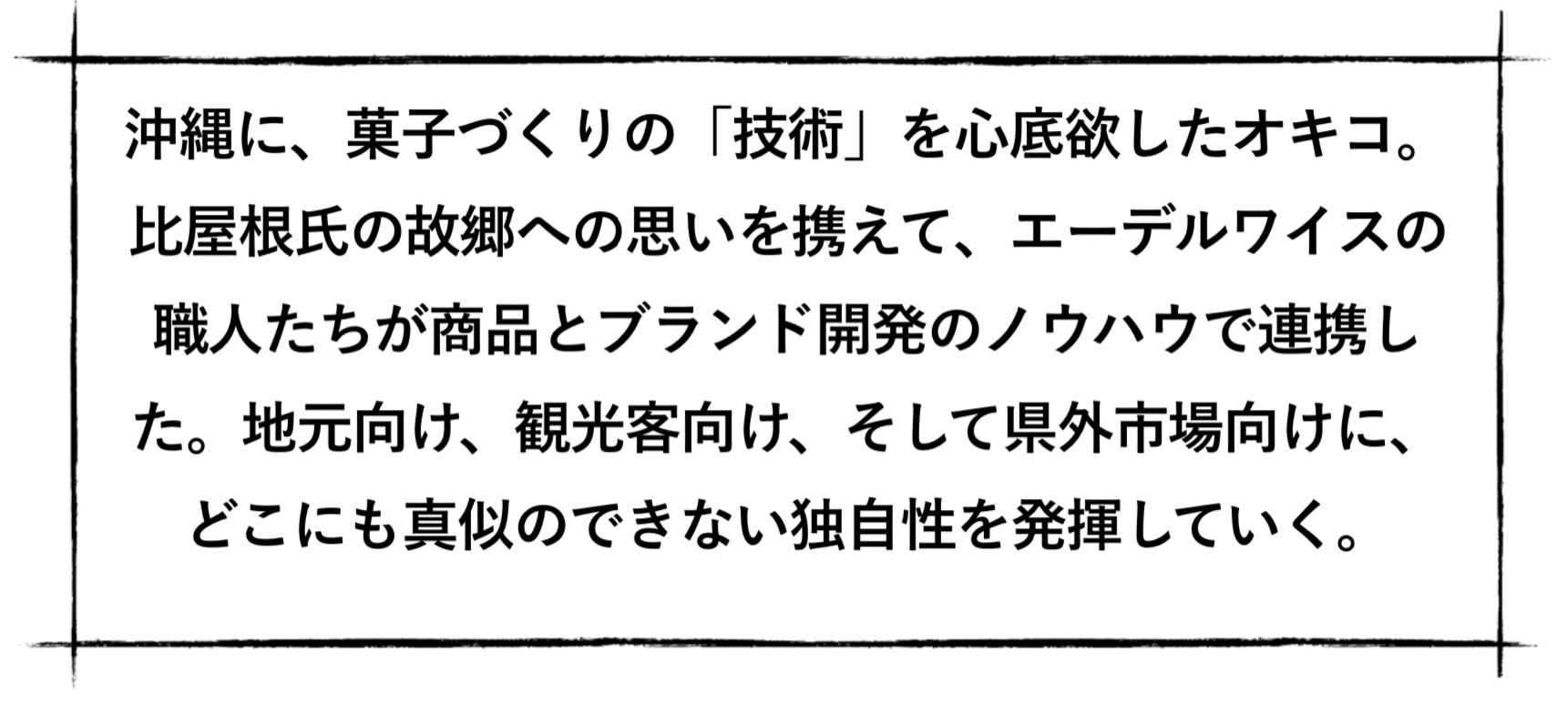

「比屋根会長から電話があった。沖縄で一緒にやってもいいと、返事をいただけた」
2014年6月11日、銘苅さんに一本の電話が入った。当時オキコ社長(現会長)だった仲田龍男さんからだった。その日は銘苅さんの母親の初七日の法要が執り行われていた。仏壇の前で電話を受けた。忘れられない日になった。
「とってもうれしかった。ちょうどウートートーして(手を合わせて)いたから、おかあにも報告した。うちの若い人たちに、ようやく成長させられる場を作ることができる。そう思った」
エーデルワイスとオキコの共同出資によって設立された新会社「エーデルワイス沖縄」は今年6年目を迎えた。エーデルワイス本体から派遣された、社長の山本憲司さんと、常務で菓子職人の山下裕士さんが技術指導で腕を振るう。

エーデルワイス沖縄の開業セレモニー=2015年2月25日、那覇市久茂地(エーデルワイス提供)
オキコにとっては、上質な洋菓子の製造とブランド開発、エーデルワイスにとっては観光土産菓子という新たな分野への挑戦の舞台。今年は、コロナ禍に見舞われた中でも、開発した「琉球焼きショコラ」が国内自動車メーカー大手の全国の販売店で提供する菓子商品の一つに選ばれた。受注した50万個超の生産が、クリスマス、お歳暮、バレンタイン商戦の繁忙期と重なり、今冬、工場は創業以来の高稼働を見込む。
エーデルワイスとオキコ、両社の目標に向かう意欲を掛け合わせながら、着実に実績を積み上げてきた。いよいよ沖縄から、品質と味で勝負できる洋菓子ブランドの展開が視野に入ってきた。
ものづくりは、人づくり
根付かせたい企業文化
「比屋根会長との出会いのおかげで、ものづくりに対する意識が大きく変わった。人の成長があることによって、企業は生き延びる。美味しいものをちゃんとつくるんだという原点に立って、魂を込めて仕事をしないと続いていかない。比屋根会長が生き様として作った企業・エーデルワイスに、我々の生き方も少しでも近づけたい」と銘苅さんはいう。
目指すのは、沖縄に技術を根付かせ、人をつくるための企業活動。オキコの社長として、エーデルワイス沖縄を立ち上げた当事者の一人として、比屋根氏から託されたバトンを握り締め、まだまだ、走り込む。
(執筆/編集:座安あきの Polestar Communications)
比屋根毅氏(1937年9月1日生まれ)
【職歴】1953年5月沖縄ひよし屋入社、55年5月ナイス食品入社、57年4月大賀製菓入社、66年3月エーデルワイス創業代表者就任、69年株式会社エーデルワイスに改組・代表取締役社長就任、2002年6月同社会長就任
【主な団体歴】大阪府洋菓子工業協同組合副理事長(1990年)、大阪府洋菓子高等職業訓練校副校長(1990年)、兵庫県洋菓子協会会長(2002年)、兵庫県菓子工業組合副理事長(2002年)社団法人日本洋菓子協会連合会副会長(2004年)、尼崎商工会議所副会頭(2012年)
【表彰歴】第5回近畿洋菓子コンテスト第2部優良賞(1962年)▷第6回近畿洋菓子コンテスト第1部最優秀賞(63年)▷第7回近畿洋菓子コンテスト優勝(64年)▷第16回全国菓子大博覧会工芸文化賞(65年)▷第4回全国菓子展示品評会総裁賞(72年)▷第18回全国菓子大博覧会名誉大賞(73年)▷第19回全国菓子大博覧会菊花工芸大賞(77年)▷第1回全国洋菓子技術コンテスト内閣総理大臣賞(82年)▷第20回全国菓子大博覧会通産労働大臣賞、菊花工芸大賞(84年)▷ワールドケーキフェア世界洋菓子連盟会長賞(86年)▷第2回全国洋菓子技術コンテスト農林水産大臣賞(87年)▷第21回全国菓子大博覧会技術優秀賞(89年)▷ジャパンケーキショー内閣総理大臣賞(92年)▷第22回全国菓子大博覧会総裁工芸文化賞(94年)▷食品衛生功労賞(94年)▷日本食生活文化賞銀賞(94年)▷石垣市民栄誉賞(97年)▷ベルギー王国王冠勲章オフィシエ章(2002年)▷兵庫県技能顕功賞(02年)▷神戸市産業功労賞(04年)▷食生活文化賞金賞(06年)▷兵庫県知事表彰(労働・技能功労)(07年)▷神戸市市政功労者表彰(09年)▷食品産業功労賞(09年)▷尼崎市産業功労者表彰(10年)▷旭日双光章(10年)▷ベルギー王国レオポルド2世勲章コマンドール章(12年)▷兵庫県勢高揚功労賞(16年)▷神戸新聞文化賞(17年)▷従六位に敘する(20年6月)